知と交流で築くアクティブシニアの居場所(千葉県柏市 一般社団法人セカンドライフファクトリー)
公開日:2025年7月18日 09時00分
更新日:2025年8月15日 13時55分
知的活動・身体的活動・社会交流の3要素を取り入れた健康麻雀
千葉県柏市のJR柏駅から程近くのビルの一室には、和気あいあいと「健康麻雀」に取り組むシニアの姿がある。麻雀といえば男性のイメージが強いが、参加者の7〜8割は女性である。真剣な眼差しで牌(パイ)を見つめる人もいれば、時折ワッと笑い声が弾け、室内は熱気に包まれている。
これは、の「脳トレ健康麻雀講座」の風景である。麻雀を通じて知的機能を活性化させる習慣を身につけ、認知症予防を目的としたプログラム。初代代表理事の故・矢冨直美氏(元東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員)によって考案された。
「脳トレ健康麻雀講座」は、火曜から土曜まで時間割がびっしりと組まれている。入門コース、ステップⅡ、ステップⅢ、実践コースとカリキュラムが整備されており、講師やサポーターが丁寧にサポートするため、初心者も安心して参加できる。1講座500円という手頃な受講料も人気の要因である。
この健康麻雀講座には、週平均で350〜400名が参加している。口コミによって受講者が増え、1教室では手狭となったため、昨年から教室スペースを拡張し、2教室体制へと移行した。講座の冒頭には10分間の筋トレ体操が行われ、体を温めたのちに健康麻雀を始めるという流れ。知的活動、身体的活動、社会交流の三要素がそろったプログラムだ。
現・代表理事の中谷(なかや)明氏は、「認知症予防効果というよりは、社会参加という副次的効果のほうが大きいと感じています。皆がワイワイ集まってコミュニケーションを取ることで、広い意味でのフレイル予防につながっているように思います」と語る。


東大の生きがい就労プロジェクトから生まれた法人
SLFは、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の「生きがい就労プロジェクト」に参加したメンバーによって設立された法人である。2010年にIOG、UR都市機構、柏市の三者協働により、「エイジングインプレイス」という理念のもと、超高齢社会に対応するまちづくりを目指す「豊四季台プロジェクト」(柏プロジェクト)が始動した。その一環として、2011年より「生きがい就労プロジェクト」が開始された。無理のない働き方を実現するため、少人数グループによる短時間労働を基本としたワークシェアリングを導入し、生きがいづくりを主な目的としていた。
約3年間にわたる生きがい就労プロジェクトの終了後、その研究成果を継承する形で、2013年にSLFが設立された。プロジェクト参加者のうち、団体設立に賛同した約100名がSLFの創設メンバーとなった。初代代表理事には東大の矢冨直美氏が就任した。
2017年には東大柏キャンパス近くにあった事務所から、現在のJR柏駅近くのビルへ拠点を移し、同年に中谷明氏が二代目代表理事に就任している。
なお、IOGの飯島勝矢氏が全国展開しているフレイル予防活動は、生きがい就労プロジェクトの参加者に対して健康調査への協力を呼びかけたことから始まった。プロジェクトの参加者の約50名がフレイル予防サポーターの第1期生である。
設立から11年が経過し、SLFの活動は、当初の就労支援から、元気シニアがセカンドライフをいかにクリエイティブに過ごすかというテーマに変化している。というのも、生きがい就労を基盤とした仕事紹介業務は、2016年に発足した柏市直轄の「」がイニシアチブを取って進めているためだ。SLFは、同協議会の構成メンバーとして、助言を行う立場で参画している。
SLFの現在の活動について、中谷氏は、「フレイル予防と認知症予防をベースにして、元気シニアの社会参加を促し、ワクワク感のあるイベントや講座を企画しています。それが最終的に健康維持や社会貢献につながればと考えています。肩肘を張らず楽しくやっています」と語る。
多彩に広がるSLFの学びと活動
SLFの主な活動を紹介する。看板講座は、前述の「脳トレ健康麻雀講座」である。参加者の6〜7割が口コミによるもので、健康麻雀を入口として他の活動に参加する会員が多い。
年に1回開催される「ホームページ制作講座」も好評を得ている。10回のコースでホームページ制作の基礎を学べる内容であり、受講料は10回で1万円と低価格に設定している。
HP事業部では、外部からのホームページ制作を受託している。理事の久保潤一氏は、「NPOや町内会、小規模店舗などから依頼を受けています。ITベンダーでは費用が高くつきますが、SLFではホームページ運用方法も伝え、自分で管理できるようにすることで費用を抑えています」と話す。
「大人の学び直し講座シリーズ」では、多様な講師陣が活躍している。例えば、「貯筋運動のすすめ」は、米国で長年筋肉の研究に従事したSLF会員・北澤俊雄氏が講師を務める。「東京七福神めぐり」は、千葉県ウォーキング協会認定ウォーキング指導員のSLF会員・中村禎宏氏が担当する。
他団体との連携にも積極的で、「新緑の鷲野谷歴史散歩」は柏観光プロダクション、「スマホで広がる!元気シニアのセカンドライフ講座」は市民公益活動団体「虹色未来大学」との共催である。
農業グループの活動は、「ニンニク事業部」「梨援農グループ」「ブルーベリー援農グループ」「SLF農ある暮らしグループ」に分かれ、それぞれ黒ニンニク栽培、梨とブルーベリーの援農、農業体験などを行っている。サラリーマン時代と異なることに挑戦したいという人に人気のプログラムである。
「わいわいサロン」は、仲間づくりを目的とした自主運営のサロンである。例えば、「生成AIを楽しもう!」「投資を楽しもう!」など、関心のある分野で集まり、楽しく社会参加を目指している。
また、シニアの健康や生きがいづくりに関する講演会も不定期で開催している。

拠点・発信・事務局の新陳代謝──SLFの特長
SLFの会員数は約1,600名、メール会員が約800名、うち約600名が実際の活動に参加している。男女比は男性4割、女性6割。年会費は無料とし、講座ごとに参加費を徴収する形を取っている。
「補助金は受けていません。有料講座を通年で企画し、大きな利益は出さずとも、赤字にならないように運営しています。一番の収入源は健康麻雀です。他の講座も含めて1回500円程度に設定し、"ワンコイン講座"をキャッチフレーズにしています」と中谷氏は語る。
広報担当の久保氏と東(あずま)善弘氏は、月1回発行の『SLF通信』の編集をしている。会員インタビューの際、よく聞かれる声は、「SLFには拠点があるのが良い」ということだ。
東氏は、SLFの特長を次のように語る。「まず1つ目は、事務所という物理的な拠点があること。2つ目は、定期的な発行物・情報発信があること。3つ目は、運営事務局に新陳代謝があること。この3つがそろっている団体はなかなかないと思います」。
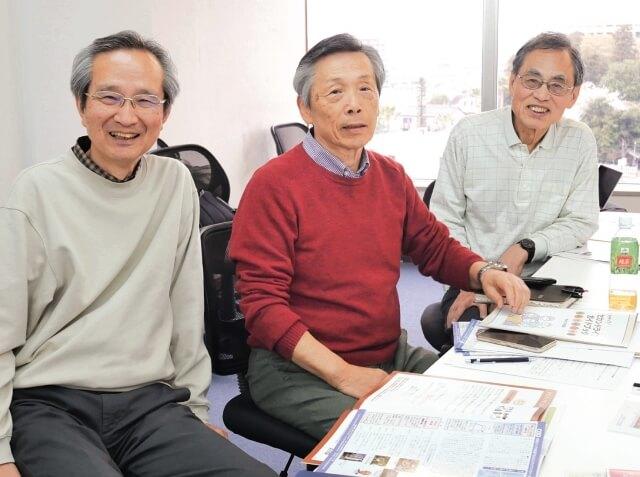
中谷氏はこう続ける。「今後も、認知症予防とフレイル予防を理念とし、アクティブな地域活動を具体化していきます。課題としては、会員数は1,600名を超えていますが、実際に活動に参加しているのは600名程度で、活動の場を広げる余地は大きいです。今後の掘り起こしが課題です」。久保氏も「情報は閲覧するけれど、活動に参加していない潜在会員がまだ多くいます」と指摘する。
"活動の場の掘り起こし"という点で今後注力していくのは、この秋から始める「大人の寺子屋シリーズ」である。会員が自らの経験や知識を生かして講師となり、講座を企画する。「難しい話を、わかりやすく、面白おかしく講義してください」と呼びかけている。すでに、仕事で特許に関わっていた元技術者の「特許の話」、造船工学の出身者の「南極観測船・宗谷の話」などが企画されているという。
柏市は都心通勤者が多いベッドタウンで、現役時代には地域と関わりが薄かった人も多く、実際にSLFを通じて地域活動を始めた人も少なくない。数ある地域活動団体の中で、SLFが選ばれる理由は、東大のプロジェクトから始まった法人であることに加え、定年後の時間を楽しく過ごすだけでなく、健康づくり、生きがいの創出、地域貢献へとつながる知的な活動ができる点にあるだろう。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。
