第96回 煙
公開日:2025年9月12日 08時40分
更新日:2025年9月12日 08時40分
井口 昭久(いぐち あきひさ)
愛知淑徳大学クリニック医師
私が学生だった頃、飯田線の電車を降りて天竜川の橋を渡ると我が家の煙が見えた。
久しぶりに帰郷したときに見た煙には母の予感があった。
煙の麓にはモンペを履いて割烹着をつけた母がいた。
煙突からの煙が生活の証であり、何とも言えぬ故郷を感じさせるものだった。
最近の家には煙突がない。
私が生まれ育った信州の田舎の家は空き家になっている。
村のあちこちに空き家があるらしいが、建物の外見からは人が住んでいるのかいないのかわからない。
気が付いてみれば私たちは普段の日常生活で煙に出会うことはない。
煙のない社会で生活している。
煙を出しながら燃える火が身近にあった生活は思い出の世界にしかなくなってしまった。
最近では「くべる」という言葉の意味を知らない人が増えているそうである。
じゅうのう(十能)、おき(燠)、すす(煤)、ひばし(火箸)、たく(炊く)―などの言葉も、今では忘れられた言葉だ。
私たちの世代が消えてしまえば、これらの愛すべき言葉や道具たちを思い出す人もいなくなるであろう。
煙に害があると喧伝されたのは公害問題が勃発した昭和40年代の初めであった。
そして煙が日常生活から消えていったのは家庭に電化製品が普及し始めた昭和50年頃からである。
家から煙が出ていた景色を覚えているのは私たちの世代が最後である。
昭和20年代の日本の朝は煙とともに始まり、煙と共に一日が終わった。
母が朝早くから、かまど(竈)にまき(薪)をくべて、ふいご(鞴)で空気を送って火をつけて、かま(釜)で飯を炊いた。
祖父は、囲炉裏に座り(火箸)を使い火を炊いて(鉄瓶)に湯を沸かしていた。
囲炉裏の炎から湧き上がる煙は部屋の中に充満して部屋の壁は悉く(燻されて)黒く変質していた。
台所にも風呂場にも煙突があった。
火を炊く原料は焚き木であった。焚き木は冬に備えて軒下に並べて置かれていた。
子供たちは山へ入って枯れ枝を集めるのが仕事であった。
汽車は猛煙を吐き、トラックは薪をくべて煙を吐いて走っていた。
日本は煙に満ちていた。
私の母親が死んだのは1980年であるが、母の火葬の煙が駒ヶ岳の頂上を目指して登っていった。
私は、死んだ人は煙になって天に昇っていくものだと思っていた。
そしていつか知らぬ間に周りには煙がない世界になっている。
人間の手元を離れた火は狂暴である。
山火事となって地球を襲っている。
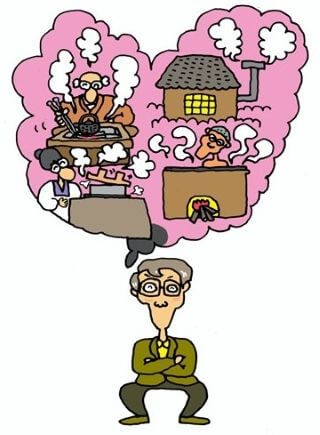
(イラスト:茶畑和也)
著者
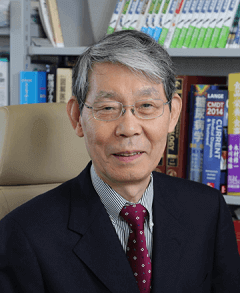
井口 昭久(いぐち あきひさ)
愛知淑徳大学クリニック医師
1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2024年より現職。名古屋大学名誉教授、愛知淑徳大学名誉教授。
著書
「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」「<老い>という贈り物-ドクター井口の生活と意見」「老いを見るまなざし―ドクター井口のちょっと一言」(いずれも風媒社)など
