老年医学の知見を社会実装につなげる(大内尉義)
公開日:2025年10月27日 15時56分
更新日:2025年12月 1日 13時31分
こちらの記事は下記より転載しました。
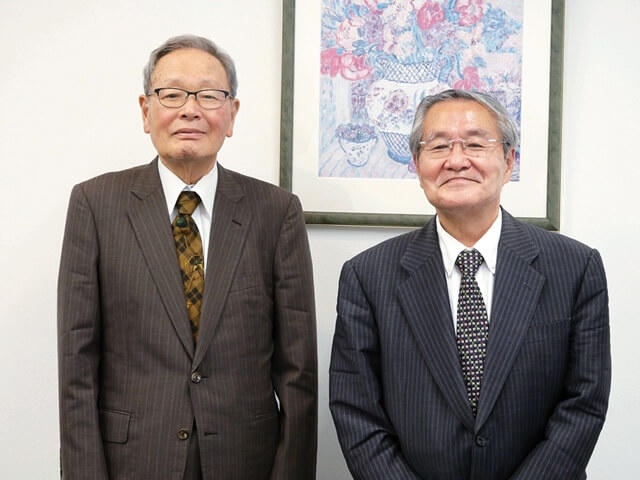
シリーズ第15回長生きを喜べる社会、生きがいある人生をめざして
人生100年時代を迎え、一人ひとりが生きがいを持って暮らし、長生きを喜べる社会の実現に向けて、どのようなことが重要であるかを考える、「長生きを喜べる社会、生きがいある人生をめざして」と題した、各界のキーパーソンと大島伸一・公益財団法人長寿科学振興財団理事長の対談の第15回は、国家公務員共済組合連合会虎の門病院名誉院長の大内尉義氏をお招きしました。
循環器から老年医学へ
大島:今号は、虎の門病院名誉院長の大内尉義先生をお迎えしました。大内先生は日本老年学会※1や日本老年医学会の理事長を歴任された老年医学のリーダーです。まず、どのように老年医学と関わるようになったのか、自己紹介を兼ねてお聞かせください。
※1 日本老年学会は、以下の7学会で構成される。日本老年医学会、日本老年社会科学会、日本基礎老化学会、日本老年歯科医学会、日本ケアマネジメント学会、日本老年看護学会、日本老年薬学会。
大内:私は岡山県の南西部、笠岡市というところの出身で、大学進学を機に上京し、それ以来ずっと東京で過ごしています。1973年に東京大学医学部を卒業し、小児科医を志しましたが、当時の東大小児科は大学紛争の影響が強く残っていて入局を断念し、内科に進みました。
当時の東大の内科は2年間の研修制度で、半年ごとに4つの内科を回るローテーション制でした。最初の半年が「老人科」で、ここで初めて高齢者医療に触れました。老人科は当時、内科の一分野という位置づけで、「高齢者を扱う内科」という臓器別医療の色彩が濃いイメージでした。
研修2期目は、どうしても小児科を諦めきれず、東京警察病院小児科で研修させていただきました。3期目は第一内科だったのですが、その頃、当時の老人科教授であられた吉川政己先生から、「老人科に入らないか」と声をかけられました。迷っていたのですが、入るなら老人科のルーツである第三内科を経験してからにしようと考え、4期目は第三内科を選びました。ここで矢崎義雄先生と出会い、私の進路は大きく変わったのです。
大島:矢崎先生は循環器がご専門ですよね。
大内:はい。当時、矢崎先生は第三内科の助手であられましたが、循環器グループの責任者に就任されたばかりで、弟子を探しておられました。
大島:第三内科といえば、東大の中核で、日本の医療界を牽引する診療科ですね。
大内:よくそう言われますが、当時の第三内科の主流は糖尿病と血液のグループで、循環器は決して主流のグループではありませんでしたが、それだけに矢崎先生の下、みなよく結束していました。循環器は臨床力が求められるのですが、大学ではなかなか習得が難しく、矢崎先生の紹介をいただき、三井記念病院で3年間、臨床経験を積みました。最初の1年半は内科一般、後半が循環器専門で、町井潔部長の指導を受けましたが、月の半分は病院に泊まり込むような生活でした。大変でしたが、その分やりがいがあったし、楽しい日々でした。
大島:外科ではよく聞きますが、内科でそれほど泊まり込むのは珍しいですね。先生はアカデミック志向、それとも臨床志向ですか。
大内:間違いなく、臨床志向です。患者さんをしっかり診たいという思いが強く、3年間の経験で、当直中にどんな患者さんが来ても動じなくなりました。三井記念病院での3年間が私を「医者」にしてくれたと、今でも感謝しています。
その後、矢崎先生に大学に帰るように言われ、1980年に第三内科に戻りました。そこで高血圧を専門にして学位を取得した後、1985年にアメリカのテネシー大学へ留学しました。メンフィスという自然豊かな町で、「高血圧と性差」をテーマに研究に没頭しました。充実した日々でしたが、翌年の春に矢崎先生から手紙が届き、その中には、「折茂肇先生が老人科の教授になられ、臨床経験のある循環器の医師を探しておられ、君を推薦したので、すぐに帰国してほしい」と書かれていました。ちょうど英語も少しずつわかるようになり、研究もデータが出始めていた時期だったので、「もう1年いさせてほしい」と折茂先生にお願いしましたが、「すぐ帰国せよ」とのご返事。急いで研究をまとめて論文を書き、1986年夏の終わりに帰国し、そのまま老人科に赴任しました。これが私の老年医学との本格的な出会いになったのです。
高齢者医療は全人的医療

大島:東大の老人科は、日本で初めて設立された老年病学の教室※2ですね。大内先生は、のちに折茂先生から教授職を引き継がれ、それ以降、老年医学に長く携わってこられました。当時、先生は「老人科」をどのように捉えていらっしゃったのですか。
※2 東大老人科は、1962年に日本初の老年病学教室として誕生した。冲中重雄氏(当時、第三内科教授との併任、のちに虎の門病院長)によって開設され、1964年より吉川政己氏が初代専任教授、1979年より原澤道美氏が2代目教授、1986年より折茂肇氏が第3代教授、1995年より大内尉義氏が第4代教授、2013年より秋下雅弘氏が第5代教授、2024年より小川純人氏が第6代教授に就任し、現在に至る。1998年に「老人科」から「老年病科」に呼称を改めた。
大内:実は、老人科で半年間研修した経験があるにもかかわらず、「なぜ東大に老人科という高齢者専門の診療科があるのか」と、正直ずっと疑問に思っていました。内科の一分野として、高齢者を診る科なのだという表面的な理解はしていましたが、その本質的な意味はわかっていなかったのです。老人科に異動し、最初の半年間は助手として、次に講師として主に病棟を担当しましたが、その中で初めて「内科と老人科は考え方が大きく異なる」と実感しました。高齢者医療では、いわゆる「全人的な医療」が必要で、患者の社会的側面や心理も考慮する必要があり、また、臓器だけでなく生活機能まで含めて診なければならない。やはりこの「生活機能をみる」というのが、老年医学・高齢者医療の本質だと思います。この2点に気づいて初めて、「なぜ東大に老人科、老年病学教室があるのか」が理解できました。
大島:私も長寿医療センターに赴任した際に、同じようなことを感じました。これまで大学で行っていた医療は、「病気を診て、病態を診て、改善を目指す」ことが前提でした。生活を基盤にした医療の視点や、終末期への備えは、ほとんど考慮されていなかったと思います。「終末期に絶対に至らせてはならない」という考えだけがありました。しかし実際には、高齢者に限らず、人は誰しも否応なく終末期を迎えるものです。そこまで見据えて診療にあたらなければ、高齢者医療は完結しないということに気づかされました。
大内:私も研修医1年目の最初の半年間の研修では、そうした理解には至りませんでした。その後、高齢者の心身と生活を総合的に評価する「CGA」(高齢者総合機能評価)という概念が出てきました。これは1930年代からイギリスで発展してきた考え方です。
大島:CGAには、本当に衝撃を受けました。「高齢者医療とは、まさにCGAである」と思いました。
大内:単に「生活機能をみる」のではなく、CGAはそれを科学として確立し、誰もが実践できる体系にまで引き上げた。その点が非常に重要だと思います。
高齢者医療と社会とのつながり
大島:以前から疑問に思っていたのは、「なぜ日本老年医学会は社会に目を向けているのか」ということです。その視点は、年々確実に広がっていて、産官学民が一体となって取り組むという姿勢が、さらに強まっていると感じます。2025年6月の日本老年学会総会に参加し、そのことを強く実感しました。
大内:老年医学は、まさに高齢者のための医学です。高齢者は社会的な存在であり、社会環境が診療や予後に、若い人よりもうんと大きく関わってきます。つまり、高齢者を適切にマネジメントするには、社会全体を視野に入れる必要がある。臓器単位で診る医療では、そうした意識は生まれにくいのです。繰り返しになりますが、高齢者医療では、全人的視点が不可欠で、生活機能もみる必要があるため、自ずと社会との接点が重要になってきます。だからこそ、社会とのつながりに焦点を当てる考え方が大きく出てきたのだと思います。
大島:今、超高齢社会に直面し、行政も産業界も、高齢者の抱える課題にどう対応するかに苦慮しています。それに対して、学会の立場からどうアプローチしていくのか。いわゆる疾病を基軸にしながら、解決策を示していくのか。
大内:私たちが目指すのは、一言で言うと、「健康長寿社会」です。国民の一人ひとりが年を重ねても元気で、天寿をまっとうする社会。その実現には、医療だけでは限界があります。健康長寿の秘訣のひとつに「運動」がありますが、「若い頃から運動しましょう」と言っても、なかなか習慣にはなりません。ならば、自然に歩きたくなる仕組みをつくる。たとえばイベント会場を駅から少し離したりして、生活の中に活動量を取り込む仕掛けが必要です。つまり、社会全体の仕組みを変えていく必要がある。
建築界も高齢者に関心を寄せています。なぜなら、家やまちのあり方を変えることで、健康長寿を支える社会づくりが可能になるからです。また、産業界も大きく変わっています。たとえばスーパーマーケットなどで、「フレイル健診」のスペースを設けているところがあります。スーパーはそうしたスペースを提供する代わりに買い物をしてもらえるわけです。こうした仕掛けが新たな産業やビジネスの機会につながります。老年医学や高齢者医療の分野を、新しいビジネスチャンスと捉えている企業は多いと思います。
大島:企業がそこまで意識しているのは頼もしいですね。ただ、健康長寿社会をデザインしていく際、日本全体を1枚のグランドデザインとして描くのは難しいと感じています。地域ごとに人口構成や地理、文化、地域資源などが大きく異なるからです。そのため、地域ごとに将来像を描き、そこに産業界・医療界・行政がそれぞれどう関与するかの役割を考えるべきだと思います。
大内:おっしゃる通りですね。老年医学と社会とのつながりを、日本全体の枠組みで考えるのは難しいです。ですから、これからは「コミュニティ」が鍵になります。人口5〜10万人の規模の自治体あるいは行政区単位で、行政・産業・医療が連携する体制をつくることが最も重要だと思います。「まちづくりによって健康長寿を実現する」─これが基本的な考え方になると思います。

学会の役割と社会実装
大島:日本老年学会や日本老年医学会は、そうした日本の将来像の中で、どのような役割を果たしていくのでしょうか。リーダーシップをとる存在なのか、理論的な支柱となるのか。
大内:どちらも担うべきだと思います。学会として、まずはアカデミアとしての理論的支柱を築くこと。そして、その知見を社会に実装していくこと。この両輪が、学会のあるべき姿だと考えます。特に、行政との連携なしには前に進めません。たとえば、東京大学の飯島勝矢先生が中心となって進めている「フレイルチェック会」は、もう全国100か所ほどで開催しています。また、筑波大学の久野譜也教授とともに立ち上げたでは、行政と強い連携を構築しています。姉妹団体であるには多くの自治体が加盟していて、「コミュニティで健康づくりをする」という考えを持つ首長の方々が非常に増えています。
大島:その取り組みはどんどん広がっているのですか。
大内:日本全体で考えるとまだこれからですが、エビデンスを構築していくと、「わがまちも」という自治体が増えてきます。今はその過渡期だと思います。
「いかに社会に役に立つのか」の視点で
大内:学会としても、老年医学の知見をいかに社会実装につなげるかが重要な課題です。2018年に日本老年医学会が「老年医学推進5か年計画」をつくりましたが、私は新しい課題として「社会実装」を加えるよう提言しました。その結果、2024年に始まった新たな5か年計画では、「社会実装」の方向性が盛り込まれましたので、今後はその実現に力を入れていくと考えています。
大島:長寿科学振興財団でも、社会実装を見据えた研究、特に社会学的アプローチを重視し、として助成を行っています。渡辺捷昭会長は、財団の役割や存在意義を常に問い、一言で言えば、「世の中に役立つのか」という視点を重視しています。研究プロジェクトが実際に社会に浸透し、価値を生み出すには、実装というプロセスが不可欠であり、それを重視して現在の事業を進めています。たとえば、Googleの慈善事業部門であるGoogle.orgの支援を受けて実施している「」では、高齢者のデジタルデバイド解消に取り組むプロジェクトに対し、1件あたり約5千万円という大型助成を行っています。
大内:基礎研究も重要ですが、総花的に助成を分配するのではなく、大型プロジェクトとして、社会実装を視野に入れた研究を掲げられたのは、時代の先を見据えた進め方だと拝見しています。
大島:財団の視点は、あくまでも日本全体です。
大内:日本全国で応用可能な基本理論を築き、それを地域ごとの特性に合わせて展開する─その流れを財団がつくっているのですね。そう考えると、財団の存在は非常に大きいと思います。
大島:そう言っていただき光栄です。今後も「社会に役立つ」という視点から、社会実装を目指した研究開発を進めてまいります。大内先生には、アカデミアとして、また財団の理事として引き続きご協力いただければ幸いです。本日はありがとうございました。
対談者

- 大内 尉義(おおうち やすよし)
- 1949年生まれ。1973年東京大学医学部卒業、1976年東京大学第三内科入局、三井記念病院内科医員、1984年東京大学第三内科助手、1985年米国テネシー大学医学部生理学教室Visiting Assistant Professor、1986年東京大学老年病学教室講師、1995年東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座教授、2006年東京大学医学部附属病院副病院長、2013年虎の門病院病院長、2020年虎の門病院顧問、冲中記念成人病研究所代表理事、2025年現職。専門は老年医学、循環器病学。日本老年学会、日本老年医学会理事長を歴任。東京大学名誉教授。長寿科学振興財団理事。

- 大島 伸一(おおしま しんいち)
- 1945年生まれ。1970年名古屋大学医学部卒業、社会保険中京病院泌尿器科、1992年同病院副院長、1997年名古屋大学医学部泌尿器科学講座教授、2002年同附属病院病院長、2004年国立長寿医療センター初代総長、2010年独立行政法人国立長寿医療研究センター理事長・総長、2014年同センター名誉総長。2020年より長寿科学振興財団理事長。2023年瑞宝重光章受章。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。
