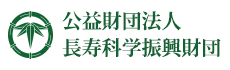いつも元気、いまも現役(洋画家 野見山 暁治さん)
公開日:2020年8月31日 09時00分
更新日:2023年8月17日 12時57分
スタジオという広い一室 パリ生活の続き
東京・練馬区の石神井川から1本路地を入り、ゆるやかな坂の途中に建つコンクリートの箱のような建物。ここは洋画家・野見山暁治さんのアトリエ兼住まい。玄関先の階段を上ると目の前に広がるひと続きの空間。壁と天井しかない。制作途中の絵が何枚も置かれ、飴色の床に落ちた絵の具までが作品ようだ。その空間の奥から野見山さんが人懐っこい笑顔でご登場。こんなにジーンズの似合う95歳はいるのか?
「柱がないから驚いたでしょう?スタジオといって、ひとつの広い部屋で、仕事もできて、生活もできて、ベッドも置く。パリでこういうのを見てきたから、日本でもこのスタイルにしようと思って。
設計は篠原一男という建築家。気むずかしい人だからなかなか引き受けないだろうといわれたので、僕は、『ひと部屋だけで間取りはいらないから、助手か学生さんを紹介してくれればいい』と言いました。そうしたら、『あなたの申し出はとてもむずかしい。これは私じゃないとできません』って。"ひと部屋だけ"というは、ボンっと投げ出された空間だから、いちばんやりがいがある。建築家冥利に尽きるということでしょう。しかし、絵の具の匂いが気になるだろうと、奥に寝室と台所、反対側に書斎と倉庫を設計してくれました」
野見山さんにとって、この空間はパリ生活の続き。ここで毎日絵を描き、パリ時代と同じカフェ・オ・レとバケットで朝食をとる。奥の書斎では、野見山さんは画家からもうひとつの顔、エッセイストになる。鋭い人間観察力とリズミカルな文にファンが多い。
西洋の油絵をひと目でも見たかった
野見山さんは17歳で福岡から上京し、東京藝術大学の前身の東京美術学校油絵科に入学した。美術学校3年のときに太平洋戦争が始まり、22歳で繰り上げ卒業。その年に陸軍へ入隊し、満州に送られた。しかし訓練中、肺の持病が悪化してしまう。内地送還され、福岡の傷痍軍人療養所で終戦を迎えた。
肺の病気もよくなり、再び東京に戻ることができたのは、終戦から3年後のこと。その年には妹の同級生だった陽子さんと結婚し、世田谷で新しい生活を始める。ある日の夕方、陽子さんがフランス政府私学留学生募集の記事を、豆腐を包んだ新聞紙の中から見つけた。フランス政府が1年間生活するだけの円をフランに替えてくれるという。野見山さんは迷わずこの試験を受けることにした。そして1952年、31歳で渡仏。
「なぜパリに行きたかったのかというと、日本は戦争のずっと以前からいわゆる鎖国状態で、セザンヌやゴッホの1点の原画も見たことがなかったからです。油絵科の生徒が西洋の油絵を見たことがないなんて、滑稽ですよね。西洋の絵の"肌"がどんなふうになっているのか、何としてでもひと目見たかった」
船でひと月ほどかかり、フランス・マルセイユ港に到着。そこから陸路でパリへ向かう。「船が地中海に入って、ナポリあたりの明かりが遠目に見えたとき、涙がボロボロ出ましたね。美術学校の生徒でパリに行けた人は誰もいないのですから。何人もの戦死者が出て、例外なくみんなパリに憧れて死んでいった。嬉し涙というよりは慚愧(ざんき)に堪えなくてね。僕だけが幸福にあずかっていいのか。少し傲慢なんじゃないか。来たことを許してくれ、という思いでした」とうっすら目に涙を浮かべる野見山さん。今でも何かの折に涙が出るのだという。
フランスの絵とその土地にはどんな関係があるのか
もともとフランス政府の留学制度では1年間生活する分の円しかフランに替えてもらえなかった。だが1年では、パリの生活に慣れた頃に日本に帰ることになる。それはもったいない、と野見山さんは妙案を思い付く。「ひと月を半分のお金で暮らしたら、2年間はパリにいられる」。野見山さんは即実行した。
パリ生活1年目は絵を描かず、美術館をまわって本物の油絵をとことん見ることにした。セザンヌ、ゴッホ、ルーベンス。パリのルーヴル美術館、そして「フランスは地方の文化も大事だ」とモーター付きの自転車を買い、地方の美術館をまわった。
「みんなは絵だけを見たいと言ったけど、僕は絵だけはなく、その土地も見たかった。フランスの油絵とその土地には、どういう関係ができているのか。どのような風景があって、あのような絵になっているのか。例えば、セザンヌが描いたサンヴィクトワールという山。本当はどういう山なのか、行って見てみたいわけです」
またたく間に2年が過ぎ、手持ちのお金も少なくなってきた。他の留学生が帰国する中、野見山さんは何とかなるだろうと、そのままパリに残ることにした。
「モンマルトルの丘でお土産用の絵を描いて売っているでしょ?あと2、3万フランしかないというときに、そこで絵を描きました。他の絵描きさんに『縄張りがあるのか』と聞いたら、『ないよ。勝手に描いていいんだ』と教えてくれて場所まで譲ってくれた。
でも絵はそんなすぐには売れない。一般の人が喜ぶ絵というのは、なかなかむずかしいですよ。日が暮れてから、場所を譲ってくれた人がモンマルトルのおみやげ屋に連れて行ってくれた。そこでは、絵の具代とキャンバス代の実費に、1日暮らしていける分を足したお金で絵を買い取ってくれて、なんとか食いつなぐことができた。どんなふうに食いつないだかよく覚えてないけど、絵で食べていけるようになるまでには、それほどかからなかったですね」
パリに来て3年後、日本から妻の陽子さんを呼び寄せた。だが、幸せな日々は永くは続かなかった。1年後、陽子さんはパリの病院で癌で亡くなる。28歳の若さだった。野見山さんは陽子さんのご家族に伝えるため、陽子さんの最期を克明に書き記した。それはのちに『パリ・キュリイ病院』(筑摩書房)として出版された。
フランスで自国の絵 東洋画に憧れた
その後、サントノーレ通り界隈の画商と契約を交わし、個展を開くまでになった。ところが3回目の個展が近づいた頃のこと。「画商が僕の描いた絵を見て、『絵が変わるのは困る。個展を1年延ばすから、全部描きかえろ』というのです。今までの僕の絵が好きで買いにくるお客がいるのに、これではだめだと。でも1年個展を延ばされると、生活ができない。だから違う画廊にこっそり絵を持っていったけど、よその画商が育てた絵描きを横取りすることはできないと断られた。向こうではそれは一切タブーです」
では野見山さんの絵はどのように変わったのか?「僕の絵がどんどん東洋風になってきたのです。パリで絵を描いているうちに、東洋画はいいなと自分の国の絵に目覚めてきた。パリの近代美術館で東洋画の展覧会あって、船が一艘、浮かんでいる絵がありました。フランスの絵描きに『あれはなんだ?』と聞かれて、『船が浮かんでいるんだ』と答えた。『この空間は?』というから『これは水だ』と。『じゃあ、これは川か?海か?』と聞かれて、『そんなことはわからない』。『どうしてこれが水に浮かんでいると思うのか?ただ船があるだけじゃないか』と言う。
僕らは1つの空間に船が1艘あって、月があれば、それだけで1つの情景を思い浮かべられる。でも西洋の人たちにはそれができない。西洋画は1つひとつ説明しないとわからないけど、東洋画はただスジが引いてあって、"ここが空、ここが水"と何となくわかる。そして、どちらを空と言おうが水と言おうが、どう見たっていい。それでいて見るものを惹きつけるというのは、いったい何だろう?
西洋の組立ての見事さに憧れてきたけれど、東洋画の"何もないところに船が一艘ある。どこにあるとかそういうのは問題なしにあるということ、存在感を与えるということ"。それに僕が傾いていって、だんだんと絵が心象的になっていきました」
この先どうなるのか。だが絵を以前のようには戻せない。このとき野見山さんは43歳。パリに来て12年が経っていた。東洋画に憧れているのだから、このまま日本へ行ったほうがいいと、大急ぎで荷物をまとめて帰国を決めた。行きは船でひと月かかったフランスは、帰りは飛行機で17時間だった。

大学で教える立場に4回の辞表を出す
帰国したのは東京オリンピックの年。パリ生活12年間で日本はすっかり変わっていた。野見山さんは"浦島太郎"だった。「自分の国のエトランゼ(よそ者)は始末が悪い」と話すように、日本の生活にも日本人にも違和感を覚え、絵の方向がわからなくなったという。
それから3、4年ほどして、大学で指導してほしいと依頼を受ける。野見山さんは絵を描く時間も減るし、教師になるつもりはないと断るが、「50歳にもなれば、教わったことを後進に伝えるべき」と説得された。はじめは武蔵野美術大学、次の年には母校の東京藝術大学で教鞭を取ることになった。
「藝大に行くまで知らなかったけど、武蔵野美大では非常勤でした。月に1、2回、気が向いたときに行けばよかった。でも藝大は常勤。常勤と非常勤の違い、出勤日数や教官会議、教授会。そういうのを知らなくて、あとで『しまったなー』って。それで1年くらいで辞表を出しました。
でも、そのときは大学紛争の真っ只中。校舎をがんがん叩くわ、団交(団体交渉)と称して怒鳴るわで、教えるどころじゃない。大学を辞めたかったけど、年寄りの先生はみんな震え上がって誰も学校に来なくなって、若手の僕が対応しなければならなかった。だから仕方なく辞表を取り下げた。僕は教師には向いていないし、第一、ほかの先生たちとうまく折り合いが付けられない。結局、4回辞表を出して、ようやく受理されたのが12年目でした」
野見山さんは藝大の教授をつとめていた50歳の頃、博多でクラブを経営する武富京子さんと結婚した。東京と福岡の別居婚という形を取り、「喧嘩もしたり仲よくしたりが30年続いた」と野見山さんはいう。2001年に京子さんは癌でこの世を去った。

戦漫画学生の慰霊美術館「無言館」
長野県上田市に戦没画学生慰霊美術館「無言館」がある。野見山さんはこの美術館の創設に尽力された。「信濃デッサン館」の館長の窪島誠一郎さんから、「戦争で亡くなった画学生の絵で美術館をつくりたいから、一緒に遺族の家をまわってもらえないか」とお願いされたことがきっかけだった。
1977年に出版された戦没画学生の遺作を集めた『祈りの画集』(日本放送出版協会)。野見山さんはこの画集をつくるため、戦没画学生の遺族の家を1軒1軒訪ね、作品を画集におさめた。窪島さんはこの『祈りの画集』をずっと心にあたためてきたという。
「最初、僕は『やめたほうがいい。遺族の家をまわるのには、とてもつらいことがある』と言いましたが、窪島さんは『覚悟している』と言う。じゃあ、2人でやりましょうということになりました。
でも本当は窪島さんのような人を待っていました。以前、『祈りの画集』で遺族の家を訪ねたとき、遺族から『私たちが生きている間はいいけれど、私たちが死んだら、この絵は捨てられてしまうだろう。それは忍びないから、絵をどこかで預かってくれないか』と言われました。そういう場所はない、と答えると遺族は泣くのです。『どこか預かるところを探すから、それまで持っていてください』。そう言わないと帰れなかった。遺族との約束が果たせるという思いもありました」
戦後は戦死者の遺族をまわる詐欺が横行していた。そのため、野見山さんが『祈りの画集』で遺族の家をまわった時には、詐欺のように扱われてつらいことも多かったという。裕福な家ほど詐欺にあったことがあるため、それから20年ほど経って野見山さんと窪島さんが訪問しても、なかなか取り合ってもらえないこともあった。それでも2人は1軒1軒、遺族に頭を下げ絵を借り受け、1997年「無言館」の開館にこぎつけた。
「最初は友達の霊を慰める鎮魂の意味がありました。でも今になって思うのは、召集までの残された期間に人はどのような絵を描くのかという、ある意味、実験として、人間の記録として、貴重な美術館だということです。絵描きの卵が卒業したら戦争に行って死ぬ。死の執行猶予のようなもので、あと1年、半年、1か月とだんだん縮まっていく。そのような期間にどのような絵を描くのか。
画集も美術館も最初はあまり評判がよくなかった。これから戦争に行く人の絵はどんなものかと期待して行ったら、普通の絵がある。親兄弟の顔とか、花瓶の花とか、平和なニコニコとした何でもない絵。『戦争中、若者はこんな気持ちで生きていたのか』と。でも逆にいうと、今から戦争に行く人が、戦争のドンドンパチパチの絵なんかを描くわけがない。やっぱり毎日見ていたいもの、親や兄弟、恋人とか別れがたい人の絵を描きますよね。つまり戦争中、みんな必死で平穏な日常を願い、離れがたい"今"を見つめていたい。それがみんな今ごろになってようやくわかってきてくれました」
「無言館」には戦没画学生の遺作の他、絵筆などの遺品、書簡なども展示されている。
自分の課題があるから今日も描く
野見山さんは60歳で藝大を退官したあとは、北九州市立美術館をはじめ、東京国立近代美術館、石橋美術館などで大規模な回顧展を開催し、精力的に創作活動を続けている。近年はステンドグラスの原画も手がけ、東京メトロ副都心線・明治神宮前駅やJR博多駅、福岡空港国際線などで野見山さんの作品に出逢える。

95歳になる今も絵と向き合う毎日。その創作の意欲はどこからくるのか。
「自分の課題があって、毎日それに向かっている。今描きたいと思っているのは、川一面に鳥が密集している。水面が見えないくらいに密集している。何かの気配でいっせいにばぁーっと飛び立っていく。その飛び立ったあとの川の静けさみたいなものを描きたい。それにはどう描いたらいいのか?何もない川を描いても、今までいた鳥たちが飛び立ったあとの静けさは表現できない。"たくさんいたけれど、今はいない、何の音もしない"というのが描きたいですね」
その課題はどんどん変わっていくのだという。ただただ絵を描きたかった少年時代から、絵に向かう気持ちは少しも変わらない。「自分の課題があるから描く。どうすればめざす表現に辿りつけるのか、毎日、毎日が実験です。だから絵にはこれでおしまいというのはありませんね」
撮影:丹羽 諭
(2016年7月発行エイジングアンドヘルスNo.78より転載)
プロフィール
- 野見山 暁治(のみやま ぎょうじ)(洋画家)
- 1920年福岡県生まれ。1943年東京美術学校油絵科を卒業。応召、満州で発病し入院、1945年傷痍軍人福岡療養所で終戦を迎える。1952~1964年滞欧、1956年サロン・ドートンヌ会員、1958年安井賞受賞、1968年東京藝術大学助教授(1972年教授)に就任(1981年辞職)。1978年『四百字のデッサン』で日本エッセイスト・クラブ賞受賞、1996年毎日芸術賞受賞、2000年文化功労者顕彰、2014年文化勲章受章。
著書『パリ・キュリイ病院』(筑摩書房)、『一本の線』(朝日新聞社)、『うつろうかたち』(平凡社)、『いつも今日 私の履歴書』(日本経済新聞社)、『アトリエ日記』『続アトリエ日記』『続々アトリエ日記』(清流出版)など多数。
編集部:野見山 暁治さんは2023年6月22日にご逝去されました。謹んでお悔み申し上げます。
転載元
公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌Aging&Health No.78